2026/01/26
「犬を飼いたいけど、自分の年齢で最後まで面倒を見られるだろうか?」
その不安、とてもよく分かります。
大切なのは、年齢の数字ではなく、万が一の時に備えて「最後まで飼う」ための体制を整えられるかどうかです。
この記事では、高齢者の方が不安を解消し、責任ある形で犬との暮らしを実現するための具体策を解説します。

【監修】うさパラ コンテンツ制作チーム
犬猫ペットのお薬通販輸入代行うさパラのコンテンツ制作チーム。専門知識を活かし、正確で分かりやすい情報発信を心がけています。 薬剤師 資格保有者が在籍。
目次
【結論】犬を飼うことに、法律上の年齢制限はありません
日本の「動物の愛護及び管理に関する法律」には、飼い主の年齢を制限する規定は一切ありません。
法律が全ての飼い主に求めているのは、年齢に関わらず、その動物が命を終えるまで適切に飼う「終生飼養」の責任です。
ただし、自治体や保護団体が譲渡の条件として、年齢の目安や後見人の有無を尋ねることはあります。
これは法律ではなく、犬と新しい飼い主の双方の未来を守るための、各団体が定めた運用ルール(ポリシー)です。
(参考文献:動物の愛護及び管理に関する法律|環境省)
高齢者が犬を飼う上で考えるべき3つのリスク①:犬の平均寿命(10~15年)と飼い主の健康寿命
犬の平均寿命は約14年。
75歳で子犬を迎えれば、その子がシニアになる頃には飼い主は90歳です。
ご自身の健康でいられる期間「健康寿命」と、犬の一生を照らし合わせ、「最後まで自分で世話ができるか」を具体的に考えることが、最初のステップです。
子犬だけでなく、落ち着いた成犬やシニア犬を迎えることも、生活の負担を減らす素晴らしい選択肢になります。
高齢者が犬を飼う上で考えるべき3つのリスク②:日々の散歩や通院に必要な体力と気力
犬との生活には、日々の散歩や、病気になった時の通院・介護など、想像以上の体力が必要です。
特に中型犬や大型犬は、かなりの運動量を要します。
ご自身の体力を現実的に考え、もし散歩が難しい日や体調が優れない時に、家族やペットシッターなど、代わりにお世話をお願いできるサポート体制を事前に整えておくことが安心に繋がります。
高齢者が犬を飼う上で考えるべき3つのリスク③:生涯にかかる飼育費用(医療費など)への備え
犬と暮らすには、生涯にわたって費用がかかります。
毎月のフード代や消耗品に加え、犬も年を取れば病気がちになり、医療費が高額になることも少なくありません。
ご自身の生活費の中で、突発的な入院や手術といった大きな出費にも対応できるか、あらかじめ資金計画を立てておくことが重要です。
高齢でも加入できるペット保険を検討するのも一つの方法です。
責任を持って飼える「最後の年齢」とは?
「責任を持って飼える最後の年齢とは、具体的に何歳ですか?」という問いに、決まった答えはありません。
大切なのは年齢の数字そのものではなく、万が一ご自身がお世話を続けられなくなった時のための「引き継ぎの計画」を、具体的に準備できているかどうかです。
それは、犬の長い一生とご自身の年齢を現実的に照らし合わせ、日々の世話を助けてくれる人の存在を確かめ、そして何よりも、あなたの代わりに愛犬の未来を託せる「後継ぎの飼い主」を正式にお願いしておく、ということです。
これらの準備を具体的に整えられるのであれば、その時が、あなたにとって犬を迎えられる素晴らしいタイミングと言えるでしょう。
年齢の壁を乗り越えるための3つの具体的な準備
① 万が一を支える「後見人(後継飼育者)」を決める
これが最も重要です。ご自身が入院したり、先立ってしまったりした際に、愛犬の残りの一生を託せる後継の飼い主を、ご家族や信頼できる方に正式にお願いしておきましょう。その際は口約束だけでなく、飼育費用や愛犬の情報を書面に残し、確実に引き継げるようにしておくことが大切です。
② 「ペット後見信託」などを活用する
ご自身にもしものことがあった時、愛犬の飼育費として財産を確実に残すための「ペット後見信託」という法的な仕組みもあります。飼育を託す後見人に、経済的な負担をかけずに済むようにする備えです。
③ 飼い主自身も健康に気を付けた生活を送ること
愛犬との散歩は、飼い主自身の健康維持にも繋がります。愛犬と一日でも長く元気に過ごすために、ご自身の健康管理を大切にすることも、飼い主としての重要な責任の一つです。
「犬を飼う 年齢制限 法律」に関するよくある質問
Q1. シニア犬を迎える場合、どのような点に注意すれば良いですか?
A1. シニア犬は性格が穏やかで、子犬育てのような大変さがないため、高齢者の方にとって素晴らしいパートナーになります。注意点としては、持病がある可能性を考慮し、定期的な健康診断や日々のケア(関節、歯、体重管理など)を計画的に行うことが大切です。
Q2. 高齢者が一人暮らしでも、犬を飼うことはできますか?
A2. 可能です。ただし、万が一の時に頼れる後見人の確保や、日々の散歩などを手伝ってくれるサポート体制を、より具体的に整えておくことが重要になります。
Q3. 入院や介護が必要になったらどうすれば?
A3. 事前に決めておいた後見人に、速やかに連絡して世話を引き継いでもらいます。そのための費用や情報を「ペット後見信託」や書面で準備しておくことが、スムーズな引き継ぎの鍵です。
【まとめ】年齢だけで諦めなくていい。大切なのは未来への準備
日本の法律に、犬を飼うことの年齢制限はありません。
しかし、法律は全ての飼い主に対し、命を終えるまで飼い続ける「終生飼養」の責任を求めています。
年齢を理由に犬との暮らしを諦める必要はありません。
大切なのは、寿命・体力・費用という現実的なリスクを直視し、万が一の時のための「後見人」や資金計画といった、未来への具体的な準備を整えることです。
その準備さえできれば、年齢に関わらず、素晴らしいパートナーと出会うことができるはずです。
関連記事
-

-
犬がくっついて寝る理由とは?背中や足元など場所によって意味があるのか解説
愛犬が、眠る時にそっと体に寄り添ってくれる。 飼い主さんにとって、それは何とも言えない温かくて幸せな瞬間ですよね。 「どうしてこんなにくっついて寝るのかな?」「甘えているだけ?それとも何か他の理由があ …
-

-
犬にしか聞こえない音とは?吠えなくなる超音波について解説
「犬にしか聞こえない音」は実在します。 愛犬が何もない場所に向かって吠えたり、その不思議な行動の裏には、私たちには聞こえない「音の世界」が広がっています。 犬の耳は、人間が拾えない高い音(超音波)や、 …
-
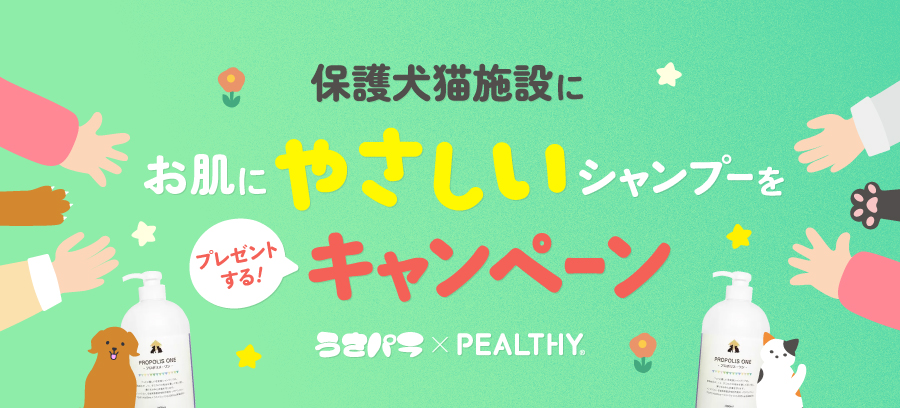
-
うさパラ×ペルシー「やさしい救世主大募集🎁プロポリス・ワン シャンプー キャンペーン」
ペットの健康に寄り添うヘルスケアブランド「ペルシー」による、ペットの肌にやさしいシャンプー「プロポリス・ワン」。 この秋、新たなボトルでリニューアルします! まずは、プロポリス・ワン シャンプーを改め …
-

-
犬の最後の気持ちが分かるサインとは?飼い主としてできる最後のケアについて解説
犬の時間は、人間の約5〜7倍のスピードで進んでいるといわれており、あっという間にその犬生をかけ抜けていきます。 愛犬との別れは、想像するだけでも耐えがたいことですね。 筆者も高齢の愛犬たちと暮らしてい …
-

-
セントバーナードに似てる犬は?性格や顔つきから見分け方について徹底解説
セントバーナードは、スイスのアルプスで救助犬として活躍してきた、がっしりとした体格と穏やかな表情が特徴的な超大型犬です。 とはいえ、日本ではあまり見かけない犬だけに、ほかの似ている大型犬と混同されるこ …


日本の法律に「何歳まで」という上限はありませんが、動物愛護法には「終生飼養の責務」が明記されています。年齢そのもので諦める必要はないものの、ご自身の健康リスクと犬の寿命(約15年)を考慮した「後見人」の確保は絶対条件だということです。万が一の時、愛犬を誰に託すか。その確実な約束と準備こそが、シニア世代が安心して犬と暮らすためのパスポートになります。
監修・うさパラ コンテンツ制作チーム